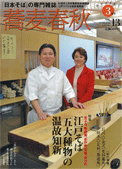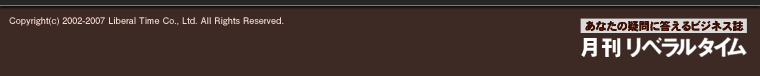リベラルタイム7月号第2特集番外編

国家の歴史はスパイスと共に…
熱帯「スリランカ」から現地レポート!
海外旅行者が、スリランカで必ず一度口にする料理に、「ブリヤーニ」がある。この国の大衆向け米料理で、日本の「炊き込みご飯」にあたるが、味と風味は全く別物。ブリヤーニに「具」らしきものは、ほとんどない。米はスパイスで黄色く色づき細長い。赤や茶色のスパイスが混ざっていて、香りは強いが味はあっさり、少し辛い。スリランカ人は、そこに、一層スパイスたっぷりの辛いカレーをかけて、手で食べる。ブリヤーニは、スパイス大国・スリランカを象徴している。
筆者が初めてスリランカを訪れたのは、今年5月のこと。インドの南東に浮かぶ北海道ほどの大きさのこの島は、かつて「セイロン島」と呼ばれ、今日では世界有数の「紅茶の国」として知られる。もっとも、広大な紅茶畑は、19世紀の英国占領下におけるプランテーションによるもので、歴史は案外浅い。この国の歴史と文化はむしろ、スパイスと密接に結びついているといっていい。それはたとえば、大航海時代の16世紀、ポルトガル人がセイロン島で採れる高級スパイスを独占するために植民地化したことや、仏教国であるこの国の仏僧の袈裟が、ショウガ科の「ターメリック」で染色されている(*)こと等から窺える。
「1日3食カレー」!
スリランカ人は、とにかくスパイス好きだ。日本でスパイスといえば「辛い」イメージがあるが、ほとんどのスパイスは、辛みはなくて、食欲をかきたてる独特の香りを持つ。今回筆者の視察の案内役をつとめてくれたのは、現地ツアーコンダクターのカマルさん。彼の好物は、やはりカレーだ。
「最近の若者はパン等を食べますが、伝統的なスリランカ人の家庭は1日3食カレー。ルーに使うスパイスは基本的に毎回同じですが、たとえば朝は肉カレー、昼は魚カレー、夜は卵カレーと具材を変えます。スパイスはたくさん使います。私の家では、基本的な味付けはクミンやターメリックが入ったカレーパウダーを使ったうえで、さらにカレー向けコショウ、サフラン、カレーリーフ、シナモンパウダー、チョウジ、トウガラシ、塩、ココナツミルク、ニンニクを入れます。使用するスパイスは、家庭によって異なります。うちでは妻よりも、義母のカレーのほうがおいしい(笑)使っているスパイスの種類に秘密があるようです」(カマルさん)
ターメリックやカレーリーフ等は、日本人にとって馴染みの薄いスパイスだが、スリランカでは、ごく一般的に販売されている。カマルさんによれば、カレーパウダーには肉用・魚用があり、価格は地域にもよるが、5〜6人前でだいたい350ルピー(邦貨換算で約290円)が相場だ。
 コロンボから車で数時間、北東へ走ると国土の中央部・丘陵地帯に「マータレ」という町がある。「スパイスの町」として知られるこの土地は、年間通じた温暖な気温と、適度な湿度がスパイス栽培に向いている。町を歩けばあちらこちらに、袋詰めにされたスパイスをキログラム単位で売る店がたつ。
コロンボから車で数時間、北東へ走ると国土の中央部・丘陵地帯に「マータレ」という町がある。「スパイスの町」として知られるこの土地は、年間通じた温暖な気温と、適度な湿度がスパイス栽培に向いている。町を歩けばあちらこちらに、袋詰めにされたスパイスをキログラム単位で売る店がたつ。
この地域には、スパイスを栽培する「スパイスガーデン」がたくさんある。マータレ近郊のスパイスガーデンで、観光客向け案内人をつとめるスラーさん(写真左)は、「スリランカ人はスパイスを食事だけでなく医療にも使う」と解説してくれた。スラーさん曰く、スリランカでしかほとんど採れない「カレーリーフ」には、コレステロールを下げる作用があり、「アラッター」と呼ばれる木のオイルには痛み止め効果、レモングラスのエキスには虫よけ効果があるという。スリランカにはインド発祥の「アーユルヴェーダ」という伝統医学があるが、その治療でもこうした植物に由来したマッサージオイルや食材が用いられている。
ただスリランカ人によれば、近年、これら「医食同源」ともいえる文化は、徐々に薄れつつある。欧米化が進む都市部を中心に、西洋の食生活を送る人や、伝統医療ではなく西洋型医薬品を使う人が増えているのだ。
日本の調味料ブームの影響は…
かわりに、スリランカ文化に対する海外からの関心は高まっている。先述のアーユルヴェーダは、日本、欧米の女性の人気を集め、リゾート地ではアーユルヴェーダ専門のホテルが脚光を浴びている。また、国内のスパイスの栽培面積と輸出量は、1970年代から穏やかな増加傾向にある。
日本はいま調味料ブームまっただ中で、その種類はひと昔とは比べ物にならないほど増えている。スリランカの対日スパイス輸出量も増えているのだろうか?駐日スリランカ大使館に問い合わせたところ、2008年までの対日輸出総額のデータが示された。これによると、05年46万ドル、06年38万ドル、07年35万ドル、08年47万ドル(08年の総輸出量は1億5500万ドル)。日本にスパイスを輸出している現地企業の代表者は、電話取材に応じ「実感はありません。スリランカ国内の市場もあまり伸びてはいないと思いますし…。景気がよいとはいえないですね」と答えた。
しかし今後は、日本とスリランカの距離が縮まっていくという見方もある。スリランカは昨年、25年以上続いた民族対立による内戦が、終結をむかえた。いまでもコロンボ市内ではあちこちに大きな銃を手にした兵士が立つが、人々は確実に笑顔を取り戻しつつある。来年は、成田ーコロンボ間の国際線が増便される。
「テロがなくなり、みんな平和になったと喜んでいます。スリランカの経済発展は、これから始まります。親日国ですから、日本のみなさんにも、スリランカのよいところをたくさん知ってほしいです」(カマルさん)
スーパーで「しょうゆ」を発見!
まだまだ遠い日本とスリランカ。ただ、両国の味の嗜好には共通するところもある。今回の視察最終日、筆者はコロンボ市内の小さなスーパーマーケットで、キッコーマンのしょうゆを見つけた。1リットルで980ルピー。隣には数種類の中国メーカーのしょうゆが並べられ、いずれも700ミリリッ トルで約300ルピー。同店ではスリランカの一般的な食用油(ココナッツ油、写真右)が1リットル約870ルピーだったことを考えると、少なくともしょうゆというジャンルでは、キッコーマンはダントツの高級メーカーといえそうだ。さらに前出のカマルさん曰く「『味の素』もありますよ。家庭ではあまり使いませんが、料理店では活用しているみたいです」とのこと。
トルで約300ルピー。同店ではスリランカの一般的な食用油(ココナッツ油、写真右)が1リットル約870ルピーだったことを考えると、少なくともしょうゆというジャンルでは、キッコーマンはダントツの高級メーカーといえそうだ。さらに前出のカマルさん曰く「『味の素』もありますよ。家庭ではあまり使いませんが、料理店では活用しているみたいです」とのこと。
調味料が文化・経済交流の架け橋になる?。将来、そんなことが、あるかもしれない。
<戻る>

国家の歴史はスパイスと共に…
熱帯「スリランカ」から現地レポート!
「1日3食カレー」というスパイス大国・スリランカに飛んだ本誌編集部員。スパイスを通じて、「医食同源」の文化に触れた。(本誌・栗原将実)

海外旅行者が、スリランカで必ず一度口にする料理に、「ブリヤーニ」がある。この国の大衆向け米料理で、日本の「炊き込みご飯」にあたるが、味と風味は全く別物。ブリヤーニに「具」らしきものは、ほとんどない。米はスパイスで黄色く色づき細長い。赤や茶色のスパイスが混ざっていて、香りは強いが味はあっさり、少し辛い。スリランカ人は、そこに、一層スパイスたっぷりの辛いカレーをかけて、手で食べる。ブリヤーニは、スパイス大国・スリランカを象徴している。
筆者が初めてスリランカを訪れたのは、今年5月のこと。インドの南東に浮かぶ北海道ほどの大きさのこの島は、かつて「セイロン島」と呼ばれ、今日では世界有数の「紅茶の国」として知られる。もっとも、広大な紅茶畑は、19世紀の英国占領下におけるプランテーションによるもので、歴史は案外浅い。この国の歴史と文化はむしろ、スパイスと密接に結びついているといっていい。それはたとえば、大航海時代の16世紀、ポルトガル人がセイロン島で採れる高級スパイスを独占するために植民地化したことや、仏教国であるこの国の仏僧の袈裟が、ショウガ科の「ターメリック」で染色されている(*)こと等から窺える。
「1日3食カレー」!
スリランカ人は、とにかくスパイス好きだ。日本でスパイスといえば「辛い」イメージがあるが、ほとんどのスパイスは、辛みはなくて、食欲をかきたてる独特の香りを持つ。今回筆者の視察の案内役をつとめてくれたのは、現地ツアーコンダクターのカマルさん。彼の好物は、やはりカレーだ。
「最近の若者はパン等を食べますが、伝統的なスリランカ人の家庭は1日3食カレー。ルーに使うスパイスは基本的に毎回同じですが、たとえば朝は肉カレー、昼は魚カレー、夜は卵カレーと具材を変えます。スパイスはたくさん使います。私の家では、基本的な味付けはクミンやターメリックが入ったカレーパウダーを使ったうえで、さらにカレー向けコショウ、サフラン、カレーリーフ、シナモンパウダー、チョウジ、トウガラシ、塩、ココナツミルク、ニンニクを入れます。使用するスパイスは、家庭によって異なります。うちでは妻よりも、義母のカレーのほうがおいしい(笑)使っているスパイスの種類に秘密があるようです」(カマルさん)
ターメリックやカレーリーフ等は、日本人にとって馴染みの薄いスパイスだが、スリランカでは、ごく一般的に販売されている。カマルさんによれば、カレーパウダーには肉用・魚用があり、価格は地域にもよるが、5〜6人前でだいたい350ルピー(邦貨換算で約290円)が相場だ。
 コロンボから車で数時間、北東へ走ると国土の中央部・丘陵地帯に「マータレ」という町がある。「スパイスの町」として知られるこの土地は、年間通じた温暖な気温と、適度な湿度がスパイス栽培に向いている。町を歩けばあちらこちらに、袋詰めにされたスパイスをキログラム単位で売る店がたつ。
コロンボから車で数時間、北東へ走ると国土の中央部・丘陵地帯に「マータレ」という町がある。「スパイスの町」として知られるこの土地は、年間通じた温暖な気温と、適度な湿度がスパイス栽培に向いている。町を歩けばあちらこちらに、袋詰めにされたスパイスをキログラム単位で売る店がたつ。この地域には、スパイスを栽培する「スパイスガーデン」がたくさんある。マータレ近郊のスパイスガーデンで、観光客向け案内人をつとめるスラーさん(写真左)は、「スリランカ人はスパイスを食事だけでなく医療にも使う」と解説してくれた。スラーさん曰く、スリランカでしかほとんど採れない「カレーリーフ」には、コレステロールを下げる作用があり、「アラッター」と呼ばれる木のオイルには痛み止め効果、レモングラスのエキスには虫よけ効果があるという。スリランカにはインド発祥の「アーユルヴェーダ」という伝統医学があるが、その治療でもこうした植物に由来したマッサージオイルや食材が用いられている。
ただスリランカ人によれば、近年、これら「医食同源」ともいえる文化は、徐々に薄れつつある。欧米化が進む都市部を中心に、西洋の食生活を送る人や、伝統医療ではなく西洋型医薬品を使う人が増えているのだ。
日本の調味料ブームの影響は…
かわりに、スリランカ文化に対する海外からの関心は高まっている。先述のアーユルヴェーダは、日本、欧米の女性の人気を集め、リゾート地ではアーユルヴェーダ専門のホテルが脚光を浴びている。また、国内のスパイスの栽培面積と輸出量は、1970年代から穏やかな増加傾向にある。
日本はいま調味料ブームまっただ中で、その種類はひと昔とは比べ物にならないほど増えている。スリランカの対日スパイス輸出量も増えているのだろうか?駐日スリランカ大使館に問い合わせたところ、2008年までの対日輸出総額のデータが示された。これによると、05年46万ドル、06年38万ドル、07年35万ドル、08年47万ドル(08年の総輸出量は1億5500万ドル)。日本にスパイスを輸出している現地企業の代表者は、電話取材に応じ「実感はありません。スリランカ国内の市場もあまり伸びてはいないと思いますし…。景気がよいとはいえないですね」と答えた。
しかし今後は、日本とスリランカの距離が縮まっていくという見方もある。スリランカは昨年、25年以上続いた民族対立による内戦が、終結をむかえた。いまでもコロンボ市内ではあちこちに大きな銃を手にした兵士が立つが、人々は確実に笑顔を取り戻しつつある。来年は、成田ーコロンボ間の国際線が増便される。
「テロがなくなり、みんな平和になったと喜んでいます。スリランカの経済発展は、これから始まります。親日国ですから、日本のみなさんにも、スリランカのよいところをたくさん知ってほしいです」(カマルさん)
スーパーで「しょうゆ」を発見!
まだまだ遠い日本とスリランカ。ただ、両国の味の嗜好には共通するところもある。今回の視察最終日、筆者はコロンボ市内の小さなスーパーマーケットで、キッコーマンのしょうゆを見つけた。1リットルで980ルピー。隣には数種類の中国メーカーのしょうゆが並べられ、いずれも700ミリリッ
 トルで約300ルピー。同店ではスリランカの一般的な食用油(ココナッツ油、写真右)が1リットル約870ルピーだったことを考えると、少なくともしょうゆというジャンルでは、キッコーマンはダントツの高級メーカーといえそうだ。さらに前出のカマルさん曰く「『味の素』もありますよ。家庭ではあまり使いませんが、料理店では活用しているみたいです」とのこと。
トルで約300ルピー。同店ではスリランカの一般的な食用油(ココナッツ油、写真右)が1リットル約870ルピーだったことを考えると、少なくともしょうゆというジャンルでは、キッコーマンはダントツの高級メーカーといえそうだ。さらに前出のカマルさん曰く「『味の素』もありますよ。家庭ではあまり使いませんが、料理店では活用しているみたいです」とのこと。調味料が文化・経済交流の架け橋になる?。将来、そんなことが、あるかもしれない。
* 大使館によると、今日、市場で販売されている袈裟はターメリックでは染色されていない。ただし、いくつかの寺院では、伝統的手法に基づき、ターメリックによる染色でつくられている。
<戻る>